���������������@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��������������
�@�@�@�@�@�@�@�@2025�N���A��o�R
���������������@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��������������
���̖͂ʓ|�ȕ���
Google���Łu�L��������A��o�R�v�Ɠ��͂��Č�������Ƒ����g�b�v�Ńq�b�g����Ǝv���܂��B
�i�g�b�v�ɂȂ��Ƃ�������܂���HNEXT�����߂ɂ����^�C�g���̂������ł��j
�܂�������������
===============================================================�@
�@�@�@�@�@�@2025�N1��1�� �i���j�@�� �@�@�@�|6���@�@I���@H���@O�c��6��
�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���_�R 1016m�@�@
�@�@�@
�@�@�@�@�@�P�Ⴒ�����o�R�A���o�����ŎR���Ȗؑ[�g�ʼn��R
===============================================================
�P��̂������o�R�A���n�Ɍ������ԁ@�Ԃ̃K���X���܂�Ȃ�����
�撅3�䎟�X�ƎԂ������A�x�x���Ă���Ƃ����₽���������Ȃ��̂ŕ����ɔY�B����7���ŏo��
���Ԓ����Ő����6:30���̃y�[�X�Ń��b�N���o���B6:10������Ζʂ̔����ɐԂ��������ꂾ����
����ōēx�h���h�������ɕύX�A����͒�����E��������J��Ԃ������B
�R���|6���A�����Ƃ��Ă���Ɨ₦�Ă����̂ő̂����đҋ@���Ȃ��班���Ԃ����܂肾�������x�ԐΕx�m�R���B���Ă����
56���ɓˑR�Ԃ݂𑝂������ɉ_�̏�̋P������������C�Ɋۂ݂��������B�����Ăق�̐��b�Ŋ������Ă��܂�(;_;)
��̃e���X�Ɉړ����Ă��`���̂��y�������������č��x��9���œȖؑ[�g�ʼn��R
���N�͉��₩�ȓV�C�ŐV�N���}���邱�Ƃ��ł���
��N�͒Z�����ǏI����Ă݂�Ƃ��낢��Ȃ��Ƃ��N���Ă����N�͒��������̂�����������
���N���y�����v���o�ň�N��U��Ԃ�邱�Ƃ����҂��ăX�^�[�g�ł�

4:30�@�@�@�Ȗؑԏ�o
5:25�@�@�@650���@5:30
5:58 �쐼��������@6:00
6]:17 ����@�@6:25
6:38 �R������̃e���X�@�@7:35
8:12 �Ȗؑ�{��o��
8:26 ���╪��@�@8:30
8:54 H511
9:29 �ȖؑR�Ԃɖ߂�
===============================================================�@
�@�@�@�@2025�N1��8�� �i���j�@�� �@�@�P��
�@ �@�@�@�@�@�����x 1144.8m
�@�@�@�@�@��L�˔����ʼn���
===============================================================
���������X�^�b�h���X�^�C���������̂Ő�R�ɍs���Ă݂����Ȃ���
�R�ŏo��������������x�͐V�������ł����̂ōs���Ղ��Ȃ�܂�����ƕ����Ă����̂Ŏ����Ɏ���
�m���Ɏԗ��͑������̂̏a�ؕ��ʂɂ������ɕ��ē����x��O�܂ō����ň�C�ɍs�����Ƃ��ł���
14�N�Ԃ�̓����x�����Ǒ�L�˂̒��ԏ�͂���ȑO�Ȃ̂őS�R�L���Ɏc���Ă��Ȃ�����
�X�^�[�g�����瑷�c�����͒ʍs�~�̊Ŕ������Ȃ��Ƃ��낾�����A
���͓����x�͍Ō�̐��N�͑��c�������肾�����̂ō�������߂͂���������̌v�悾����
�����x��1144m�̒�R�ł͂��邪���፷��1000m���肻�����2000m���o��̂Ɠ����o�����y���߂�̂�����
�����}�o���͌l���͂��邯�ǎ��ɂ͂��܂芴�����Ȃ��������ߑ��c��������̓o���ɕς��Ă��܂���
�W�X�Ɠo����3���ڂŃX�^�[�g�������̃t���[�X��E�����A
�����ڂŃ`�F�[���X�p�����ē~���o�����܂肪�悭���K�ɓ����R���ɓ���
�R���̋L�����v���o���Ȃ��A�Ƃ肠�����ו��������ăV�F����h���߂ɕς��ĎR���Ɍ�������
���傤�ǒN�����Ȃ��Ȃ����R���ƓW�]�u���������ĎR���ɖ߂���

�R���Ōy�H�㉺�R�A�V�C���\��ʂ�ߑO�������̐��ꏙ�X�ɓݐF�̉_�͗l�ɕς�肾����
�o����ł܂�������̂��߂����炩�ȓo�肾�����̂łƂĂ��y�Ɋ��������~����i�������Ȃ��̂ŕG�ɂɔY�܂���邱�Ƃ��Ȃ��������B
�����ڂŃA�C�[�����O���܍��ڂŖh���߂��V�F���ɕς��Ē��ԏ�ɖ߂���
�g�C���̗��ɐꂪ����̂ŌC�Ɠ���ނ����ď���̕������������ԏ�����Ƃɂ���
�����쉷��ŕ��C�ɓ���O�ɏo��Ɠ����x�͐�_�ɕ����Ă���
8:10
��L�˒��ԏ�o
9:43 ������ 9:55
10:31 �����R���@10:41
10:57 �����x���W�]�u�@11:10
11:25 �����R���@�@11:45
12:09 �����ځ@12:18
13:24 �Ԃɖ߂�
===============================================================�@
�@�@�@�@�@2025�N1��11�� �i�y�j�@���� �@�@�P��
�@ �@�@�@�@�@�@���ȎR
2530.7m
�@�@�@�@�@�@������o�R����艝��
===============================================================
����4:00��7:40��
��������ԏ�͊��ɖ��Ԃ炵��1km���̒��ԏ�Ɏ~�߂��A���g�̌�̉��₩�ȉ����̓y�j���A�ߏ�̓o�R�҂͂���Ⴀ�E�������^^;
�Ō��7�q�͏��̐ᓹ���s
���ȎR�͎���30���N�Ԃ�A�����͊��삩��o�X�ł������Ƃ����L���Ɏc���Ă��Ȃ��A
����̕����ϐ�������̂Ōi�F������Č�����v����V�[�����Ȃ�
�o�R�����犥��̂��߂����ɃA�C�[�����������10�{�܁A���ɍ����̓`�F�[���A�C�[���͂��Ȃ������A
�r���Ń~�h���E�F�A��E���O���[�v�������������ǎ��͍ŏ����甖���Ȃ̂Ŏ~�܂邱�Ƃ͂Ȃ��}�C�y�[�X�œo���A
�Ȃy�j���̂��ߓo�R�҂������A���ёт̃��b�Z���Ղ�o�邽�߃X�y�[�X���Ȃ��̂ŏꏊ�T�����C���g������
2200m����Ō�̋}�o���n�܂�A���x���オ��̂Ŕ������X�̏�ɑN�₩�l�C�r�[�u���[���f����A
�����ĐU��Ԃ�Δ����x�S�i�A��A���v�X���L�����Ă���
�R���L������V���Ĕ����x�S�i�����n���ꏊ�Ōy�H�����R�A
���x�̓R�o���g�u���[�Ɏ��X�Ɣ����x����э���ł���
�A�H�̋}�o�͐Ƃ��Ȃ��Ă��邪�܂��x�^���͂Ȓi���͊���ŕ����Ă��邽�ߕG�ɂ��Ȃ�����悤�ɍ~��
�����ƒ��܂����Ꮏ�̂��߂ɂ̓X�^�[�g���Ԃ𑁂����Ȃ�������Ȃ�����^^;
�Ƃ肠�����V�N����X�^�b�h���X�^�C���ɕς����������œ~��̍s���͈͂��������̂͊y��������
��������ԏ�ŃA�C�[�����O���ĎԂɖ߂���
�������߂Ɏ����Ă����u���V���ᗎ�Ƃ��ɂƂĂ��𗧂����B
���C�͕������ē��}���]�[�g�����𗘗p�A����Ń��X�����̂܂ܐz�K�C���^�[����ѓc�܂ő���c��͈�ʓ�������܂Ŗ߂�
���m�����̐V�쓻�͒��쑤�͏��Ⴕ�Ă��������ǂ��������͕����ɓ���܂Ŏc�Ⴊ�c���Ă���
�ʐ^�͔����x�S�i�k���x����Ҋ}�R�܂Ł@

�A�b�v�̕��͍����痰���x�A�Ԋx�@����Ɋx�A�����x�A�Ҋ}�R

8:04 �Ԃ�u�����ꏊ����X�^�[�g
8:23 ������o�R���@�A�C�[������
8:30
9:32 2110m�W��
11:42 ���ȎR�R���@12:18
13:43 2110m�W��
14:13 ��������ԏ�@�A�C�[���O��14:24
14:40 �Ԃɖ߂�
===============================================================
�@
�@�@�@�@�@2025�N1��15�� �i���j�@�܁@-2���@�@�P��
�@ �@�@�@�@�@�@�@���_�R 1016m�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�Ȗؑ�X������A���o���������R
===============================================================
��_�ɕ���ꂽ���̓��̖��_�R�A���담���ԏ�ɂ͐撅�͂Ȃ�
�Δȓ��H�͍��N�����̌Q�ꂪ�o��G�߂ɂȂ���
�Ȗؑԏ���撅�Ȃ��A�x�x���I���ēȖؑ[�g�Ŏ��t��
�������s��������̂Ń��b�N���̗͂�����Ȃ��悤�ɓo��^^;
�ꉞ���ɂ���������Ă݂����c�O������(;_;)
�r������o�����[�g�ɓ���X���ӏ܂ɂƉ�����݂����A���������܂��܂�������(;_;)
�ϐ���Ȃ��̂ʼn��̕X������㕔�X���Q�܂ł܂��A�C�[�������Œʉ߂ł��Ă��܂��悤�ł͎c�O������
��łɖ߂�R���ɒ���������_�ɕ���ꎋ�E�͖����A�l�̋C�z���Ȃ��̂ŃT�b�T�Ɖ��R
�v���Ԃ�ɒ��o�����������Ă݂��A������肾�����Ⴊ���邪�₽�����͂Ȃ�
�G��݂��Ȃ���فX�ƍ~��Â��Ȓ��ԏ�ɖ߂���
 �@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@
8:13 �Ȗؑԏ�o
9:03 ��ꗧ�����@9:11
9:22 ���╪��
10:01 �X���Q����@�@10:15
10:42 �R���@�|�Q���@ 10:51
11:05 ����
11:35 650m���
12:16 �Ԃɖ߂�
===============================================================
�@
�@�@�@�@�@2025�N1��16�� �i�j�@���� �@-19���@�@Y�c
�@ �@�@�@�@�@�@����Ɋx 2805m �@�@�@�@�M�R�\���H��艝��
===============================================================
�v���Ԃ�ɏM�R�\���H���爢��Ɋx�����ɁA�X�^�b�h���X�^�C���̂������ōs���͈͂��L�������
6:30�M�R�\���H����y�A�C�[���ŃX�^�[�g�A�撅�̎Ԃ͓��B
�Q�[�g�������̐ς������ѓ�����������Ɛi�ށA�ѓ��I�_�ŏ㒅��E���ŏ��̓o��䏬���R�܂ŏ����ɓo���A
�䏬�������ɑ��z���̂ڂ�n�߂����ёт����b�Z���Ղɏ������Đi�ށA�r���J�����ꏊ�Ŗk�x�A�b���A��䃖�x���P���Ă��A
�s���������������10�{�܃A�C�[����ς���A��������}�o���n�܂�
����܂łƈقȂ�Ꮏ���ς��\�ʂ����낭�Ȃ蓥�肪�キ�Ȃ����A
��������R�荞�܂Ȃ��ƕ���Ă��藎���Ă��܂��A�̗͂����Ղ���o�����������A
���ёт̋}�o�̐�ɐ��������W�]��ɔ�яo����ɕ���ꂽ���Ɉꑧ���ꂽ�A
���V���������܂蕗���Ȃ��̂Ő�D�̐�R�o�R�ɂȂ肻���ȗ\�����ǂ�ǂ�c��ށA

�����}�o���ĐX�ь��E���Đ�ʂ̍Ō�̋}�o���c�������ɂȂ���
���ς�炸�����͒��܂��Ă��Ȃ��̂Ńo�����X���Ƃ�Ȃ���ɓV�ɋ߂Â����ւƌ������A
�T�d�ɃU�C���𗊂�ɋ}�o�����Ƃ��낪���m�������ŕ���ŕx�m�R��w�i�Ɏ�p��\���A
�D�V�ɓV�_��Ȃ��|19�������ア�̂Ŋ����͊����Ȃ��ō��̃R���f�B�V�����B�����x�����㏸�����ςȂ��������A
�n�V�S���ĎR���ցA������ɂ����͊���ɉB�ꔒ�ʂ̑�n�ƂȂ��Ă����A

��̑O�ɍL���锪���x�A�R�ɐ���g���A�����ʐ^�B�e�ɔM���A
�w�悪�_�̂悤�Ɍł������o�̉�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ��Y��ăV���b�^�[�����������Ă����A
�i���o�������̂ʼn������̂��ǂ�����������Ȃ����^^;�j

���₩�ƌ����Ă��������������Έ�C�ɗ�C�ɂ܂��A�����ł���ꏊ�ł͂Ȃ��̂Ŗ��c�ɂ������lj��R��
���ȎR�Ɍ������Ĕ��ʂ��~��n�߂��A�X�ь��E�܂łْ͋�������

��q�ƍ��̊��������ŕ���Ŏ��ɕʂ�Ċ���₷���U�C�������ݐ^���ɐT�d�ɑ�����m�ۂ��Ȃ�����肵�������ɍ~��ċْ����n��
����S�A
���ётɓ���W�]��Œ��H�̏��e�A�������I�j�M���ƃo�i�i�ňꑧ�A
��ʂ�����悤�ɉ��~�A�n�ʂ���ɕ����i���������Ă��邽�ߍ�����G�ɂ͂Ȃ������Ɍ䏬���R�܂ʼn��~���Čy�A�C�[���Ɍ���
�i�����Ȃ��Ƃ����͖̂{���ɕG�ɂɂ͏�����A�قڗ\��ʂ�̎��ԂɎԂɖ߂����B����������o�R�҂̒��ł͎����ō���҂��낤��^^;
�x�x���I���ĕ��C�ɓ������Ƃ����ȎR�̂Ƃ��͌C����E�����Ƃ����̎w�S�����Ԃ������̂�������͐ԍ����ϐF���Ă����B
�����Ő���Ă���Ԃ͂����̂��������ɓ���ƌ��ɂ������A���炭����ł���Ə����F���߂��Ă����A
��̎w��Ƃ����C��t���Ă��������ƈ�҂͂������ǂǂ��C����������̂�^^;
�A�H�͌��\���C���N���Ă������LjӊO�ƌ��C�Ɏ���܂ŋA�邱�Ƃ��ł����A
�����������܂Ŕ����ƂȂ���^^;
6:32 �M�R�\���H���ԏ�o
8:11 �䏬���R�@8:13
9:12 �s�������������@�A�C�[�������@9:33
10:22 �W�]��@10:28
11:47 ���m���������@11:53
12:08 �R���@12:30
12:36 ���m���������@12:43
13:15 �W�]��@13:35
13:55 �s������������
14:29 �䏬���R�@�y�A�C�[���Ɍ����@14:44
15:37 �Ԃɖ߂�
===============================================================�@
�@�@�@2025�N1��22�� �i���j�@���� �@�@�P��
�@ �@�@�@�@�@�@�@�b�ߎR 2191m
�@�@�@�@�@�@�@�@�L�͌��o�R����艝��
===============================================================
15�N�Ԃ�̌b�ߎR�A���̍��̓S�[���f���E�B�[�N���Ɏc����y���݂ɒʂ��Ă���
���̌�c����y���ނȂ甪���x�̕����ʔ������Ȃ̂ő������̂��Ă��܂���
�����̓m�[�}���^�C���ő����Ƃ��낾�������s���Ȃ������̂�����
���̎����̌b�ߎR�L�͌����[�g�͉Ď����̒��ԏ�܂ōs�����Վ����ԏ�𗘗p
�Վ����ԏꂩ��o�R���܂����Ⴕ���ѓ���4�L���ȏ㍂�x��330m�����
�A�o�R����O�̃g���l���ŃA�C�[�������A
�I�[������1700m�܂ł͒P���Ȋ����̓o��A���������ł܂ŋ}�o�A���E�̂Ȃ��o��r���̓�A�A���A���炢�A
���x�͒Ⴂ���Ǖ��̂Ȃ��D�V�C�̂��ߊ��_�N�_�N
1900�����Ă���̎��ёт̋}�o�͊���̂��ߓ����}�ɂ���������ɂ����Ȃ��Ă���
���R�ɓW�]��ɓ����A�����Ŏ~�߂����ł��������邫�₷������̂��߂������܂ōs���Ă��܂���
���̍ō��_�܂ōs���Ă��W�]�͂Ȃ��̂����̎R�̓����A�����͓o��R�Ƃ�����蒭�߂�R��
���R���ʂ��璆�Ð�Ɍ������Ɛ��ʂɗY��ȎR�e�߂邱�Ƃ��ł���

����ł��W�]���̎肷��ɍ����Ē��H�A�ǂ��������͒P��3�l�����̐Â��ȎR�s���y���߂���������
���[���𑗂��Ă���i���O�Ȃ̂œd�g���E�����̂�������ɑ��M���Ă���邾�낤�Łj���R�ɒ���
���ёт̊J���������ォ�璆�A�Ɠ�A�̓W�]������̂ŏ������Ԃ�����
�c�O�Ȃ��琹�x�̉��ɉ_���������Ă���x�m�R�܂ł͊m�F�ł��Ȃ������B

�G�ɂ��}�Ȋ����̉ӏ��͊����邯�ǂ��Ăɔ�ׂ��������Ȃ����������B
���R�㒋�_����ŕ��C�ɓ���A���̎w�͂܂��ɂ݂��A
�A�H�͋v���Ԃ�ɍ��H�A�Ë���܂���ċA��B
�r�[����Ɉ������㍡���܂Ŕ������Ă��܂���^^;
7:15 �@�؉��Վ����ԏ�o
7:59 �L�͌����ԏ�@8:03
8:44 �L�͌��o�R��
10:00 1716m�n�_
11:42 �b�ߎR�W�]��i�ꓙ�O�p�_�j
11:50 �R������
12:00 �b�ߎR
12:05 �R������
12:10 �b�ߎR�W�]��@12:38
13:45 1716m�n�_
14:24 �L�͌��o�R��
14:56 �L�͌����ԏ�
15:40 �Վ����ԏ�Ԃɖ߂�
===============================================================�@
�@�@�@2025�N1��29�� �i���j�@�܂�@-5���@�@�P��
�@ �@�@�@�@�@�@�@���_�R 1016m
===============================================================
������ɎR�s�\�肪�������̂ő̗͉����Ŗ��_�R�����b�^�������肾����
����ǂ����x�͒Ⴂ����_�������������Ɨ₽�����ł������ƕ�����������
�쐼�������ΔȂ܂ŋv���Ԃ�ɂ���Ă��܂����B
���ԏꂪ�����Ȃ��Ă����̂Ŋ��҂��ĕX������ŎR���ցA�X��Ќ�����Ȃ�����(;_;)
�R��-5���A��̃e���X�Ōy�H�㎞�Ԃ����������̂ŃT�b�T�Ɠ쐼�����ւƂ܂����
����ɂ͋O���Ԃ��オ���Ă������U��Ԃ�������ɍ~�肾����^^;
P706�Ŏ��Ԋm�F���ē쐼�������ΔȂɍ~��郋�[�g�ւƌ������A�r���u��4�����ɍ~���n�_��ʉ߂����
�o���炵�����͋C�ɕς��
�͗t�̑͐ς����Ζʂ������̂Ń`�F�[���X�p�����ĉ��~�AP445�̊��ŖP���߈ꑧ
���E���Ђ炯��̂͂��̊�ꂾ����

�ēx�c��̔������~��ΔȂɋ߂Â��ƃV�_�������ǂ��n�߂邯�ǂ܂��܂��ז��̃��x���ł͂Ȃ�����
�ΔȂɍ~��Ԃɖ߂�ƒ��Ɠ������̎Ԃ���������
8:12 �Ȗؑԏ�o
8:49 H511
9:12〜9:17�@����@
9:28 ���╪��
9:50 �����o��
�X����������Ď�łɂł�
10:36 �n�m�w��
10:51 �R���@-5��
11:08 ��̃e���X�o
11:18 ����
11:30 �쐼��������
11:49 P706�R��
12:00 P706
12:17 �u��
12:51 H445
13:15 �ΔȂɍ~���
13:35 �Ԃɖ߂�
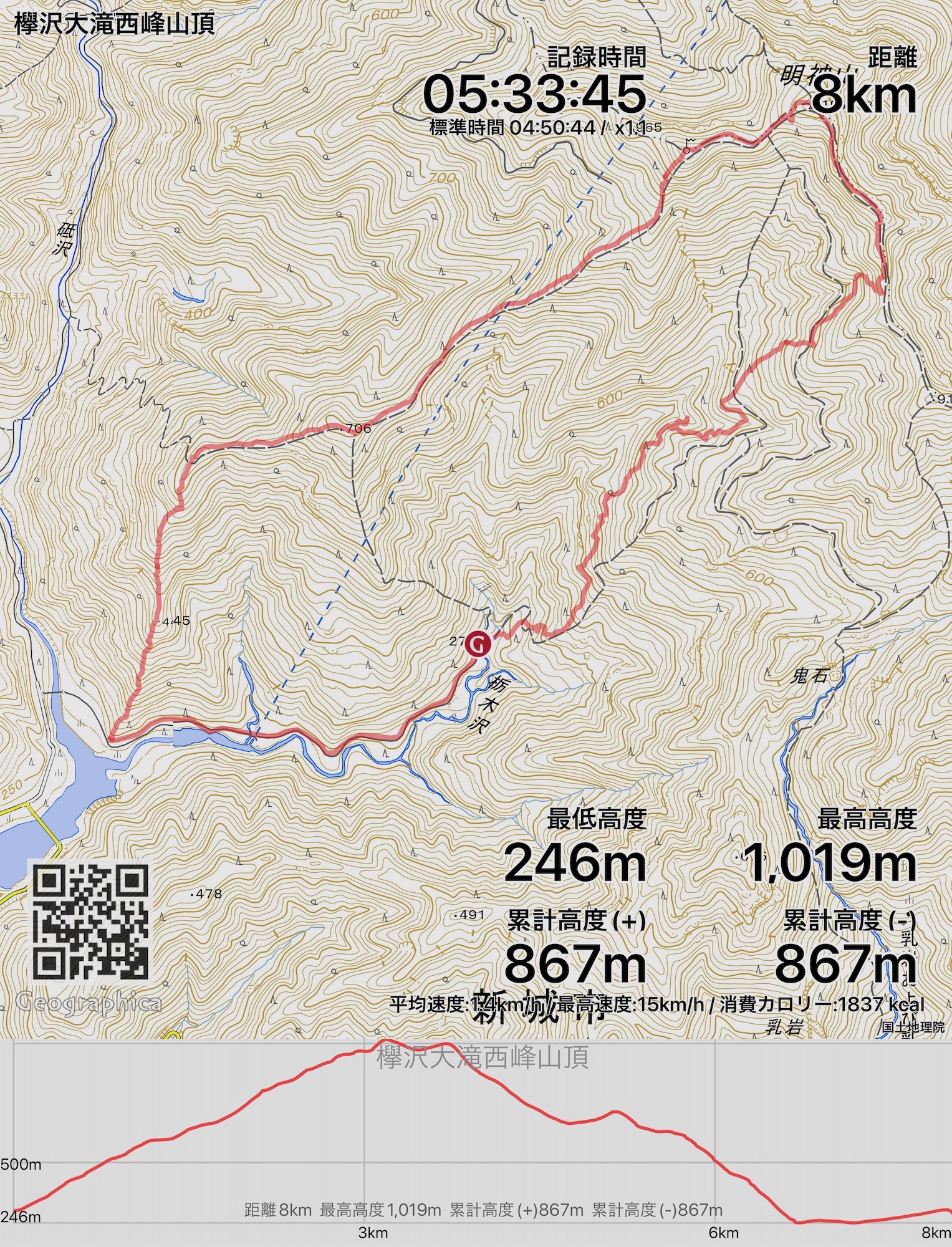
===============================================================�@
�@�@�@2025�N1��31�� �i���j�@���@�@Y�c
�@ �@���O��r�W�^�[�Z���^�[����l���ێR1293m〜�������R1418m〜�厺�R1587m
===============================================================
��������������ґO���A��N�������[�g
6:30���O��r�W�^�[�Z���^�[���X�^�[�g�A
���ɉ��x��������n������ւƓo��A�������܂�Ȃ��₽�������Ȃ�����
���I��o���ŃA�E�^�[��E���Ōl���ێR�܂Ŋ��𗬂��ēo���A�R����ɂ͐V�����������ł��Ă���
�i�g�C���t�@���R���ނ͎����A��j
�悪�����̂Ń����N�{��m���ւ�100m�ȏ�~��A�r������x�m�R�������n�߂��B
�l���ێR����4�قǃs�[�N���Ĕ��Γ��������ŃG�X�P�[�v���[�g�͂Ȃ��Ȃ�\��ʂ�̐i�s
�����ɉ������R�ɂ��A��������o�R�҂Ƃ���Ⴂ�������n�߂�
�����ɂ��V�������Ȕ������������A�l���ێR��o���Ă���Ƃ��Ɍ������̂͂��̏����̂悤������
�ׂ̑O�厺��O�͕x�m�R�̓W�]�ӏ��ŎB�e���Ԃ�����
�O�厺����Ō�̓o���1���Ԃ��܂肵�đ厺�R�ɓ����A���̎��ԂɂȂ�ƕx�m�R�ɂ͉_��������n�߂�
�x�m�R�ړI�̏ꍇ�͂���������o���ĉ��ق����ʐ^�I�ɂ͓K���Ă��邩��
�i�r�W�^�[�Z���^�[����厺�R�܂�1000m�قǂ̕W�����ł��������}�o�j


���z�H����ɖ߂�V���̔�����50�����炢�~�茢�z�H�����ɂ��Čy���H����
��N���������������A�艷��̒��ߐ莞��(��t17:00�j�܂łɎԂɖ߂邱�Ƃ��ł���
6:35 ���O��r�W�^�[�Z���^�[�o
7:14 ���I��o��
8:14 �P�Z�̃^���@8:16
8:58 �l���ێR1293m
9:12 �l���۔���
9:29 �����^�{��̓�
9:51 �o���̓�
10:10 �V���K�O�`��1191m
10:34 �i���N�W��̓� 1241m
10:49 ������̓��@1278m
11:07 �����@11:16
11:34 �������R�@1418m
11:40 �������R����
11:58 �O�厺�R�@12:03
12:14 �j����
13:00 �厺�R 1587m 13:08
13:15 ���z�H����
14:10 ���z�H�����@14:31
15:29 �p�ؑ�o��
15:56 ���O��r�W�^�[�Z���^�[�߂�
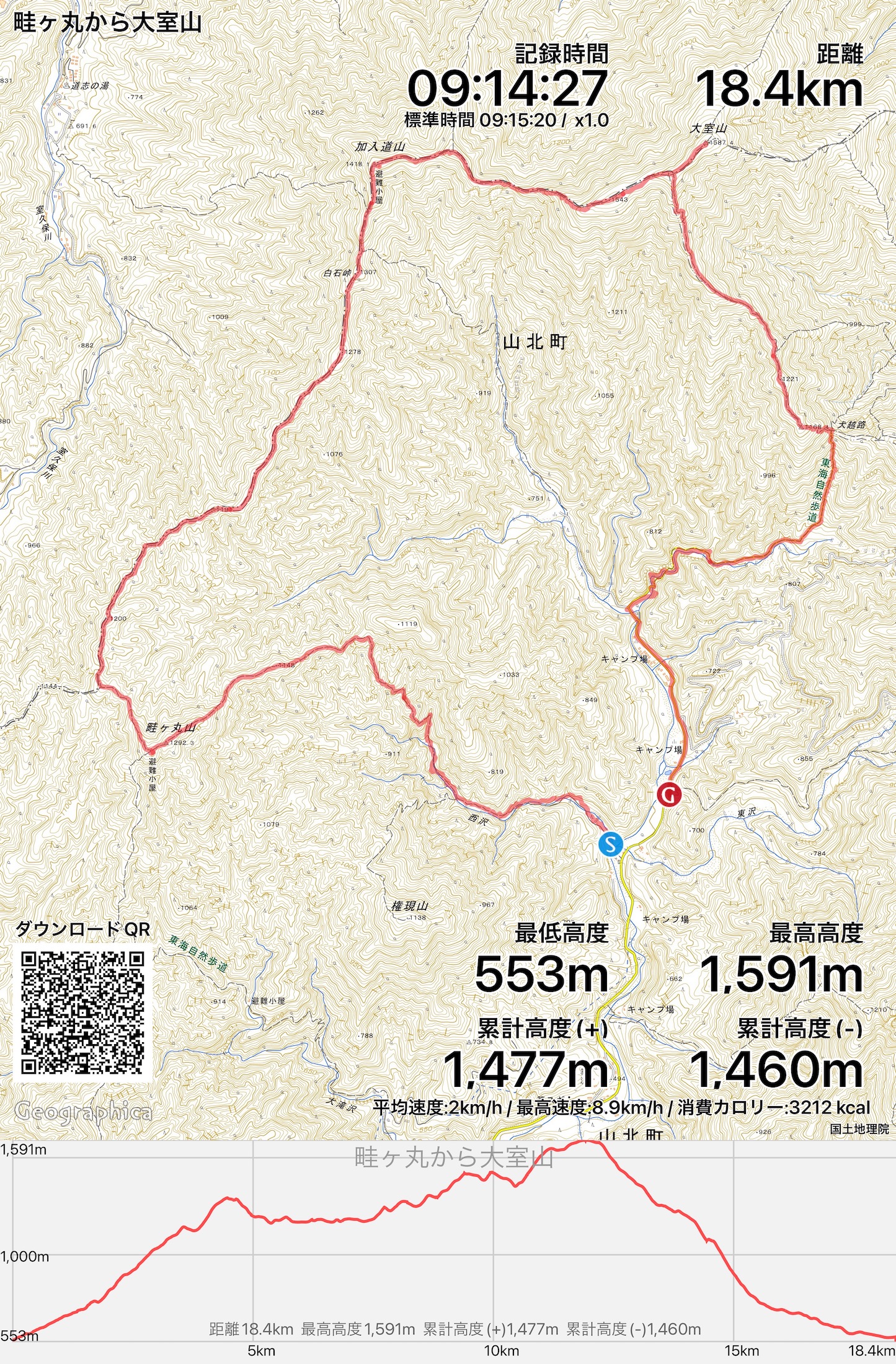
===============================================================
�@
�@�@�@2025�N2��5�� �i���j�@�܂�@-8���@�@I��
�@ �@�@�@�@�@�@�@���_�R 1016m
===============================================================
�Ƃ̕��͋��������ǂ������͂قږ������̑��艷�x�͒Ⴂ�B
�s�v�s�}�̊��g�炵�����X���Ɋ��҂��ēȖؑԏ�ɁAI������������̂œ�l�ʼn�邱�ƂɁB
�r��400m������̉�������������ꏊ�ł͐����C�������o���Ă����ɂ��邾���Œg���������B
700m�����肩��͊���ɂȂ蒆���������Ă���͍~��ƂȂ����B�����X����������܂��܂��c�O������
��łɏo�ĕ����₽���Ȃ����̂ōēx���C���[�h��lj��B
����̔n�̔w����ĎR���A�}�C�i�X8���B�~�ᐁ��Ŏ��E�O���C�̂܂�
��̃e���X�ŏ��e�Ǝv����������ȓV��Ƀ��b�N�����Ă��Ă�����オ��Ȃ��̂ŃT�b�T�Ɖ��R
���ǃA�C�[�������邱�Ƃ��Ȃ�����Ă��܂����B
����̕X������ł̓A�C�[���������Ƌْ�����ꏊ��ʉ߂���̂Œ���
�~��̒��𒓎ԏ�����Ⴕ�Ă��邩�Ɗ��҂������������薾�邭�Ȃ�n�ʂ̘I�o�����Ȗؑ���
�ʐ^�́@�R���Ɣ����ڔn�m�w��iI������̃u���O����j


8:16 �Ȗؑԏ�o
8:53 H511
9:17 〜 9:22 ����@
9:33 ���╪��
10:10〜10:40 �X������
10:53 �n�m�w��
11:08 �R�� -8���@11:19
12:08 �Ȗؑ�{��o��
12:23 ���╪��
12:48 H511
13:23 �Ԃɖ߂�
===============================================================�@
�@�@�@2025�N2��12�� �i���j�@���܁@-2���@�@�P��
�@ �@�@�@�@�@�@�@���_�R 1016m
===============================================================
���g�������Ă���̂ŋv���Ԃ�ɓu�����P���L���k�s���đ������ɍs����
�u��ѓ������̎�O�ɎԂ��߂ėѓ�4�����悩��P���L���[�g�Ɏ��t��
�������ő�ɓ��荞��̒���Ζʂɂ͐ϐႪ������҂Ń��N���N�A
�Ƃ���ǂ���ɓ���O�ɓ�������A�����̑��Ղ�������
���͈ȑO�̂悤�Ȕ��͂��铀���ł͂Ȃ����������G��Ԃ̏�Ԃ���

�Ζʂ��`�F�[���X�p�����ċ}�o���g���o�[�X���[�g�ɏo�đ�̏㕔��ʉ߂��ğO�JP706�R�������ԃ��[�g�ɏo��
�����߂�X�Y�K�^�ѓ��܂ł̃P���L������o���A���̎��Ԃ͂܂���ŗz�������Ă������ߏ��������H�肾����
�ѓ��ɏo�ĕX�������ɍs���Ă݂����������͂܂��܂��_���������A
�߂��Ė��_�̌��܂ōēx���𗬂��Ȃ���o�����Ď�łɏ��Ƃ������肵���ϐ�A
�������������o�����₽�����������������̂܂ܓo���A
����ł͐��x�Ȃǂ��z�ɋP���Č�����

��������ŏォ�畗���Ȃ��Ȃ芾�𗬂��قǂł͋�C�ɕς����
�����C���v�͒ቺ�X���ɂȂ��Ă���
�R��-�Q���A�����Ȃ��̂œ��ʊ����Ȃ��̂ł��̂܂܌y�H�ƃ��[���^�C��
����Ō����Ă�����A���A�����ɂ����Ȃ����̂Ŏ����ڂ̕X���͂�߂ēȖؑ[�g�ł̉��R�ɕύX����
�`�F�[���X�p�����Ă���̂Ŋ���s���͂Ȃ����Lj����|���ɋC�����Ȃ��牺�~
�r���Ȗؑ�̑�ꂾ���͂���Ă݂��A
�������̂ق��������Ԑ������Ă�������ɉ������Ăĕ���Ă���̂ŕs���ł͂���
�≺�ɂ͑傫�ȑ����X�̃u���b�N���͐ς��Ă�

�`�F�[���X�p���ĐÂ��ȎR�����~��Ȗؑԏ�̑�ɂ���Ċ�⓹��ނ����Ă���Ə��J�������n�߂�
20���قǕ����ĎԂɖ߂�x�x�����Ă���Ɩ{�~��ɂȂ肢���^�C�~���O�ʼn��R�B
8:15 �u��ѓ�������O�ɒ���
8:35 �u��4����
857 �P���L��ɂ͂���
9:30 ���@9:50
10:12 �P���L������t��
10:40 �X�Y�K�^�ѓ��o���@10:45
11:00 ���_�̌�
11:18 ����@
11:35 �R���@12:00}
12:37 �Ȗؑ�{��o��
12:50 �S���z����@12:55
13:00 �Ȗؑ���@13:20
13:35 H511���F����
14:04 �ȖؑR�@14:11
14:35 �Ԃɖ߂�
===============================================================�@
�@�@�@2025�N2��15�� �i�y�j�@���� �@�@�P��
�@ �@�@�@�@�@�@�@�������R 2730m
�@�@�@�@�@�@�@�@�j�����艝��
===============================================================
���j�����y�j���̕����V�C�\���₩�Ȃ����������̂ŏo������
���b�Z�������ŏ����x��ē����������Վ����ԏ�͂��łɖ��ԁA�܂��Â����������v�������Ă���
���ԏ�̈�ԋ��ɉ�������Ŏx�x���J�n�A���x�͒Ⴂ�������Ȃ��̂ŗ₽���������Ȃ�����
�ѓ���1.5�L��200m�قǍ��x�������Ė���G�̓o�R���ɓ����A
���Ⴊ�����₷���̂ł��̂܂ܓo�肾���A�u�h�E�̐��O����͐ϐႪ�����Ă���
���邱�Ƃ��Ȃ��A�C�[���Ȃ��Ă���ʂ݂��߂Ȃ�������ɓo���A�����H�藎�����B
�n�Ԃ��߂��đ�M�����ւ̔����ɏ���O���炵������ϐ�A���X�c�{���ɂȂ�
�����ŃA�C�[�������ċ}�o�Ɍ��������������s�m���Ńc�{���ɂȂ�A�ʒu�������Ɣ����o���Ȃ��_���[�W�Ŕ�J���܂�
��҂����̓A�C�[�������ł������肵�������Ńh���h���o�����Ă����Ɏ��т̒��ɏ����Ă���
��Ԃ������ă��J�����B������������Ɍ������ēx����H�点�Ȃ������i�߂�
�挎�͒��q�ǂ��������ǂ܂����Ƃ͎v�����������҂ɂȂ����r�[�ɑ̗͂̓��Z�b�g����Ă��܂�������������
��ŏ�ɂ���Ƃ��������オ��Ƒ�M�����O��Œǂ������Ă�������҂��������łɎR�����������ĉ��R�̂��߂̐H����������
�ؑ]��x�A��ԎR�A��A���v�X����R�Q���������P���Ă����B
�����Ō��߂Ă�����A��o�R�̓P�ނ̃^�C�����~�b�g�����O���������i�F�ƓV�C�̗ǂ��ɖ������d�������R���Ɍ����Ă��܂����B
���ӎ��Ƀ��J�����O���Č��������������������[�B
��ŏ�̊���͓����Ă��ăT�N�T�N�ƕ����Ղ���ꂽ�����ɖ����Ȃ��o���ł��ď�������
���܂��ɋ������Ȃ��K�x�ɑ̂��₵�Ă���ĉ��Ȃ���o���ł����A���������{���Ō�̓o���҂��Ǝv��^^;
�������œƂ��߂Ŏʐ^�^�C���B


���R��17������Ɨ\�z���Ď�ł����Ƃɂ����B�����~��ɂ��Ă��P�ނƒB���ł͔�J�x���قȂ�
���藎����悤�ɎΖʂ��~���M�����Ōy�H���Ƃ���
���̌㏬�����łĂ����Ɏ�܂�r���ŗ��Ƃ������ƂɋC�Â��ēo�蒼�����ԃ��X������������
��ʂ���Ă͂��邪�����ɔ���Ă������܂������𗬂��Ȃ���17�������߂��ɂ܂��z�����邤���Ɍj����ɉ��R�ł���
����G�ƈ���Ăقǂ悭�ł߂�ꂽ����͒i�����Ȃ��Ȃ邽�ߕG�ɂ��������邱�Ƃ��Ȃ�����
���Â��Ȃ����ѓ��𑖂�悤�ɎԂɖ߂����B�v���Ԃ�Ƀo�e�C���̓o�R�ɂȂ����������x�͑傫��
6:40 �Վ����ԏ�o
7:12 �j����o�R���@7:17
7:42 �Ԃǂ��̐�
8:43 ��c��
9:17 �n�Ԃ�
9:57 ��M�����@10:17
10:33 ���˔���
12:50 ���P�x����@13:03
13:43 �������R�@13:55
14:10 ���P�x����@14:14
15:18 ��M�����@15:40
16:03 �n�Ԃ�
16:24 ��c��
16:53 �Ԃǂ��̐�
17:04 �j����@17:14
17:33 �Ԃɖ߂�
===============================================================�@
�@�@�@2025�N2��20�� �i�j�@���� �@�@Y�c�@S��
�@ �@�@�@�@�@�@�@��i�R 2693m
�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@�@�@�����˒��ԏ��艝��
===============================================================
���x�͒Ⴂ���Ǖ����Ȃ��̂ŗ₽�����������ɍs���ł���
���ёт̓`�F�[���X�p�ʼn����ɓo���A���s�҂͓قŌ�a��̕��ɋȂ������̌���蒼�i���ĎO���ڕ���
��a���ւƓ������B�r���̓c�{���ŏ���������ւ͕��Ńg���[�X�͏����Ă������ǎ��X���ݔ����Ȃ��番��ɏo��

�}�W�b�N�A���[�̎B�e
���̂܂܃g���o�[�X�C���ɓo�����Ό�������ɓ��������̂ň�C�ɑ��Ό����̕���܂œo���x�e
�d�b�ňʒu�m�F������܂���a��Ƃ̂��ƂȂ̂ŐH����ʐ^���B��Ȃ��瓞���҂��������B
���s�҂��������̂ŏ��e����Ό��܂ōs���A�C�[���̕t�ւ�������
�Ό������g���o�[�X���čL��ɂ���i�R�ւ͓o�R���łȂ����ڎR���֓o����

���Ό������i�R�R���Ɍ��������ƍ��x��
300m��
�ϐႵ���ӏ������Ȃ��̂ő������s����ɂȂ�̂����܂ĎR���ɓ����A
�������Ȃ��������䖝�ł�����x

���R�J�n�A�{���ɐϐႪ���Ȃ�(;_;)
���R�͎R�������a���Ό����i�{�R��4���ډ�����j�܂ō~��悤�Ƃ��������Ⴊ�Ȃ���
�����ɂ��������̂Ŋ���̂���ꏊ�𗘗p���č~��Ă���Ԃɍ~�肷���ă��[�g�ύX�A
�ϐ�̂���ꏊ��T���đ����Ɍ����鏬�R�Ɍ������č~��͂�̌Q�����ď��V��˕W���O�ɍ~�肽�B

��i�R�����ʂ��C�����ǂ����R��
���[�g���ЂƓo�肵�Č�a���������قւƉ���ĉ��R����
���X�₽�����������łĂ����Ƃ������邱�Ƃ͂���������
�X�^�[�g���牺�R�܂ŃE�F�A�͕ς��Ȃ������̂ł��傤�Ǎs�������x�������Ă����悤��
����Ȃ��Ƃ͒�����^^;
4:19 �����˒��ԏ�o
5:20 �ꍇ��
6:16 ��
6:45 �O���ڌ�a�뒆
6:55 ��a���
7:23 �{�R���S���ځ@�@8:15
8:35 ���Ό����@9:02
9:12 ���Ό�
9:55 ��i�R�R���@10:26
12:09 ���V���
12:29 ��a�����
12:42 ��
13:39 �ꍇ��
14:17 �Ԃɖ߂�
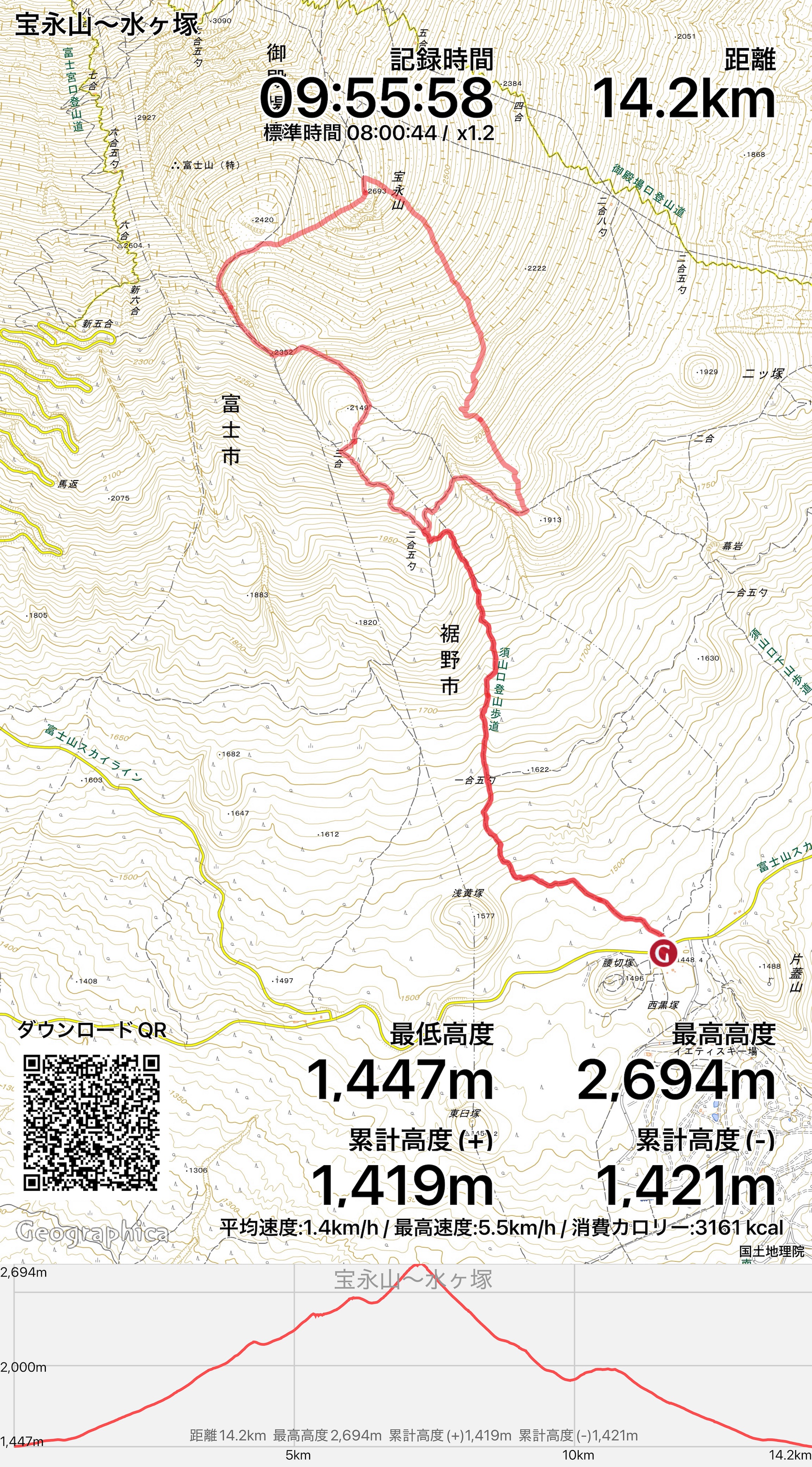
===============================================================�@
�@�@�@2025�N2��26�� �i���j�@�܂�@0���@�@�P��
�@ �@�@�@�@�@�@�@�@���_�R 1016m
===============================================================
���T�����牷�x���オ��J���~�葱���\�ł��B���_�R�̕X���X�������������ł��I���̊����Ȃ̂ō��T�͖��_�R��^^;
���⏬�담���ԏ�̓[���A�Ȗؑԏ���[���A�����Ȃ������������Ȃ��m���ɂ���ȋC���ł͕X�͊��҂ł��Ȃ�
����͍�N���ł��I�N�^�̃V���c���啝�l�����ɂȂ��Ă����̂ł����N���b�N���Ă��܂���
���i������������̂ł���������o�R^^;
�����y���V���c�A�A���_�[�Ɩ������Ă����T�C�Y���傫�̂ɏ����������Ă��܂��B
�Ƃ��������̏�Ƀ��C���E�F�A�𒅂ăX�^�[�g�A�I�N�^�̃W���P�b�g�^�C�v���~�����������ɓI�ɂȂ��Ȃ��Ă���̂�
�V���c�ƃ��C���E�F�A�Ŗh���h��
�ŏ���H511m�Ń��C���E�F�A�����܂������|���₷���ƌ�����_�炩�Ȑ��n�ɋC�����Ȃ���o���A
�ŏ��̑��͊��҂����ɍ~��Ă݂���ӊO�ɓ����Ă��Ă�����Ɗ����������A

����Ȃ�X�������҂ł������ƃo���G�[�V�����ɓ������B�o���Ă���ԁA�����ϐႪ�Ȃ����X�������ӏ������邾����
�����������₽�����Ƃ̍��x�̎Ζʂłǂꂾ����Ԃ�ۂ��Ă���̂��s���ɂȂ��Ă���
�X���ꏊ�ɂ��Č��グ��Ə������Ɉ�C�ɗ������ށA�������������ϐ�Ȃ��ŏ㕔�ւ����̂܂ܓo��������
�o�R�Ƃ��Ă͈��S�ŗǂ��̂����NJy���݂��Ȃ��Ȃ���
������Ȃ��嗬�o������Ƃ肠�����R���ɁA0�����i�͉B��Č����Ȃ��̂œ�̃e���X�ŏ��e
���e�㍡�x�͂�����̑������ɍs��
�����O�������������Ⴊ���邾���A�쐼�������������̂��Ȃ���������̂����~�肾��
���ɂ͊����Ȃ������V�����P�̒ɂ݂��C�ɂȂ���
P706�R������̂����ڈ�ɉ����Ē����~�A�������̑����������ڗ������A
�㕔����ʐ^���B�������ƍ���͂��̂܂ܑ���~���̂ʼn��̕X���ɂ�����Ă݂�
���̂܂܃g���o�[�X�C���ɑ�Ɍ������č~�肽�A�ォ�猩���Ƃ��͔��͂�����悤�Ɍ���������
�����炾�Ɣ���������̂̍����ł͈�ԓ����Ă���̂ł��ꂪ���N�Ō�̍�i�ɂȂ肻�����B

�O�l���������̂Ńi�����͒����~��Ō�͓��ݐՂɂłăP���L�[�g�ɏo��
4��������u��A�Ȗؑԏ�ւƕ����ĎԂɖ߂����B
�I�N�^�̃V���c�����������₷���ƌ����銄�ɂ̓o���G�[�V�����̌͂�}�ނɂ���邱�Ƃ��Ȃ����ʂɍs���ł����B
�ʐ^�P�@�Ȗؑ���@���̓P���L����
8:10�@�@�Ȗؑԏ�o
8:45 H511
9:07 �Ȗؑ���T���@9:15
9:24 �S���z����
9:42 �����o��
9]55 �X���T���@10:17
10:30 �n�m�w��
10:43 �R������̃e���X�@11:03
11:12 ����
11:28 �쐼�������o��������
11:47 P706�R��
12:09 �P���L����T���@12:33
12:56 �P���L��o��
13:16 �u��4����
13:20 �u��
13:51 �Ԃɖ߂�
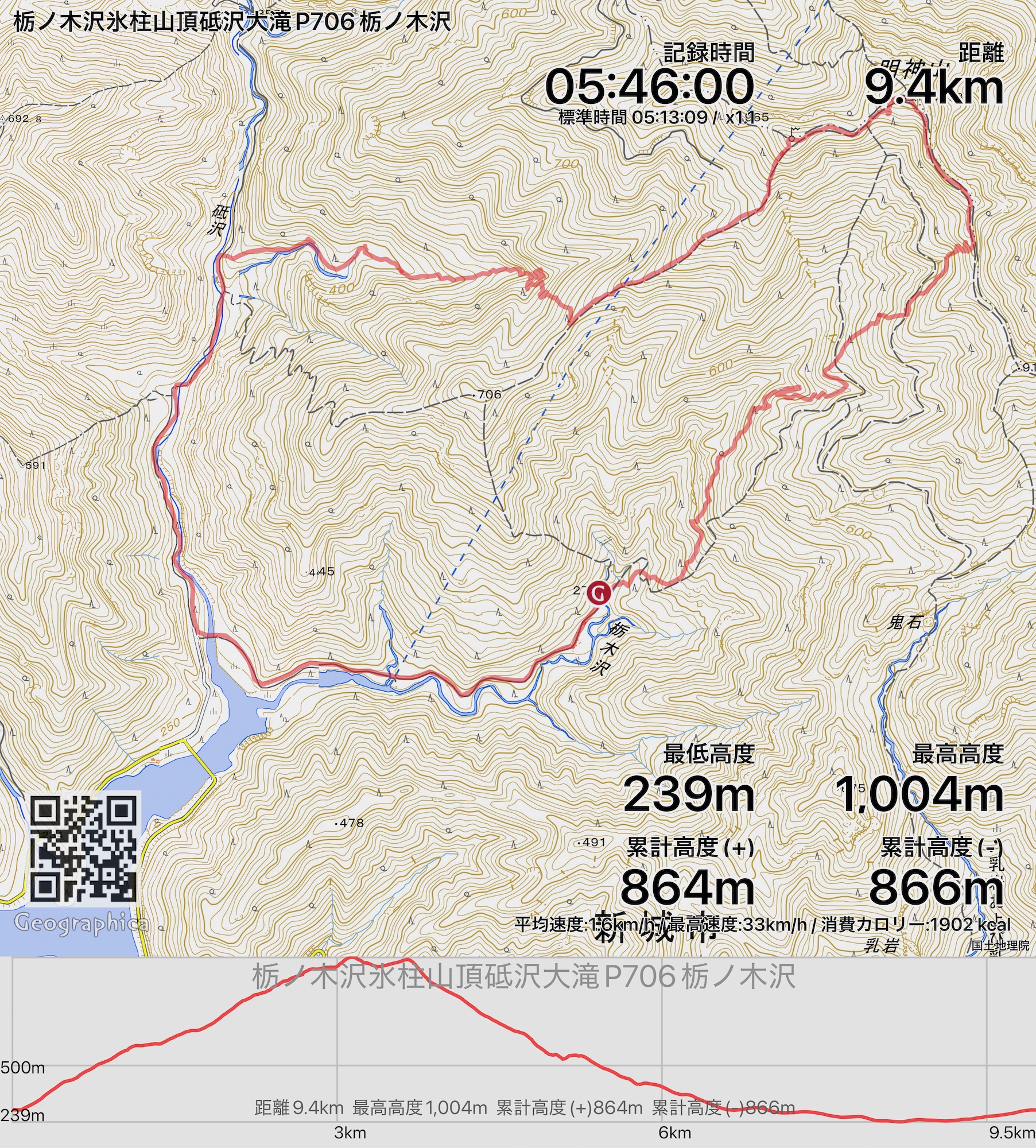
===============================================================�@
�@�@�@�@�@�@2025�N3��13�� �i�j�@���@�@Y�c
�@ �@�і��R1500m�\�x1683m�ߓ����x1736m�S���x
1736m���x1623m
===============================================================
13���ؗj���s���|�C���g�ň������Ԃ�����̂��͌��Ύ��ӂ����������̂�2�T�ԂԂ�̓o�R
�r��1�T�Ԃ͕��ׂ��Ђ��ĔM�o���ĐQ����ł����̂ő̗͓I�ɏ����s���̂���o���B
���A������l�ő҂����킹�Ă������Ő��ΌΔȃL�����v���̖і��R�o�R���Ɉړ����ēo�R�J�n
�o�R���߂��̂���l�ɌF���ł邩��C�����ĂƐ����������ăX�^�[�g�A�P���ȓo�肪�����r���㒅��E���Ń��Y���悭�o��


�R���߂�����x�m�R�����ʂɌ���e���V�������オ��A�і��R(1500m)�O��Œ��̃V���b�g���I�������Əc���ɓ���
�\�x�܂ŊԂɏ\��̊x�����菙�X�Ɋ��̃��Z�����ɂȂ��Ă����A�����͊��Ⴊ�܂���ɂ��莞�X�������ꏊ������
����U�C������o�ď\��P�x����40m�قǂ̋}�~���̍���ɂ��̑O�ォ�������ƑO���̉J�ő��ꂪ�D�Ńx�^�x�^�c���c����ԂɂȂ�C��z��
�}���~�̈Õ��̒J�Ԃɒ�������D�ŔG�ꂽ�C��͊���Ղ����܂��ɂ悭�h��ċْ������B


�킽���Ă�����140m�قǂ̋}�o�̊������A�U�C�����g�p���Ȃ��睳���o�芾�����ŏ\�x(1683m)�̎R���ɓ���
�����ł��x�m�R�̃V���b�g���y���ނ��Ƃ��ł���



�R��������ēx����Ŋ����I�����������ɕς����������̈����͕ς��Ȃ�����
���R(1686m)���琼�̖k�Ɉʒu������R��ō���̐ߓ����x�ւƉ���.���قǎ��Ԃ̃��X�͂Ȃ����Ǒ����͓D��͕ς�炸
�����ł͕x�m�R�ƍb����k�x�ԃm�x�ԐΊx���x�Ȃǂ̓W�] ���v���X�B

���R�ɖ߂�S���x(1736m)�ւƓo�蒅���A��������͓�A���v�X�A�R�ɔ����x���W�]�ł���{�����B
�ЂƂ����肨�������b����P���O�R�A�k�x�A�ԃm�x���牖���x�A�ԐΊx�A����x�Ȃǂ߂ă��t���b�V��

�Ō�̌��|���֍~��n�߂�A�D�^�c���c���̈��H�̘A���ł��̊Ԃɂ��Y�{���͓D���炯��
�i�F���f���炵���̂œD�^�ȂNjC�ɂ͂Ȃ�Ȃ��Ƃ����l���������邯�ǎ��͑�L���C
�����ō����B��̓�l�g�Əo�������B�ނ���c���c���x�^�x�^��Ԃœo���Ă��Ă��肱�̐��ςł���Ɨ�܂��ꂽ
200m�ȏ�̍~���T�d�ɑ�����T���Ȃ��玞�Ԃ������č~�������|���R�����B
�Ō�̉��x(1623m)�܂ł͔����̃A�b�v�_�E�����J��Ԃ��Ȃ���Ō��͂芊�芊�肵�Ȃ���R���ɓ������čs���͏I��
�����ɂ͒���߂����ԏ�ƎԂ������Ă����B���e��Ō�̍~��ɂ�������
�����������͂���̃��[�g�����K�ɍ~��Ă�����Ă̒�h���h���ɕς��Ζʂ����~�肽��D�̏�ɌC��u���ꏊ��T���Ȃ��牺�~�B
����ł����x1300m�O�ォ�犣���������ɕς����K�ɕ�����l�ɂȂ���S
��̌㔼�͍�Ɠ��H�ɏo�����ԏ�܂œD�𗎂Ƃ��Ȃ���߂����B
����l�̒��ԏ�ł͓r���ł������o�R�҂��������x�A��Ƃ��낾�����A�������H�ł����˂Ƌ�����Ȃ���ʂꂽ�B
���C���ł����ƈÂ��Ȃ������H�ɏo����ˑR�O�̎Ԃ̃����v���ƂĂ����ɂ���������
�{���P�ĎԊԋ���������ɂ��������B
���b�N�����荂�����^�Ԑ����Ԋԋ������ێ��������x�ŐT�d�ɑ��s���߂邱�Ƃ��ł���
�Ȃ낤��^^;
6:00 ����l�������ԏ�ō����і��R�������ԏ�Ɉ��ړ�
6:30 �і��R�������ԏ�o
7:43 �і��R1500m�@7:47
9:43 �\�x 1683m�@10:04
10:59 ���R 1686m 11:02
11:17 �ߓ����x 1736m 11:21
11:37 ���R�߂�
12:04 �S���x 1736m 12:21
13:21 ���|���R������@13:34
13:51 ���|�i�o����j1589m
14:45 ���x 1623m 14:55
14:46 ����l����
16:13 ����l�������ԏ�
16:25 �і��R�������ԏ�߂�
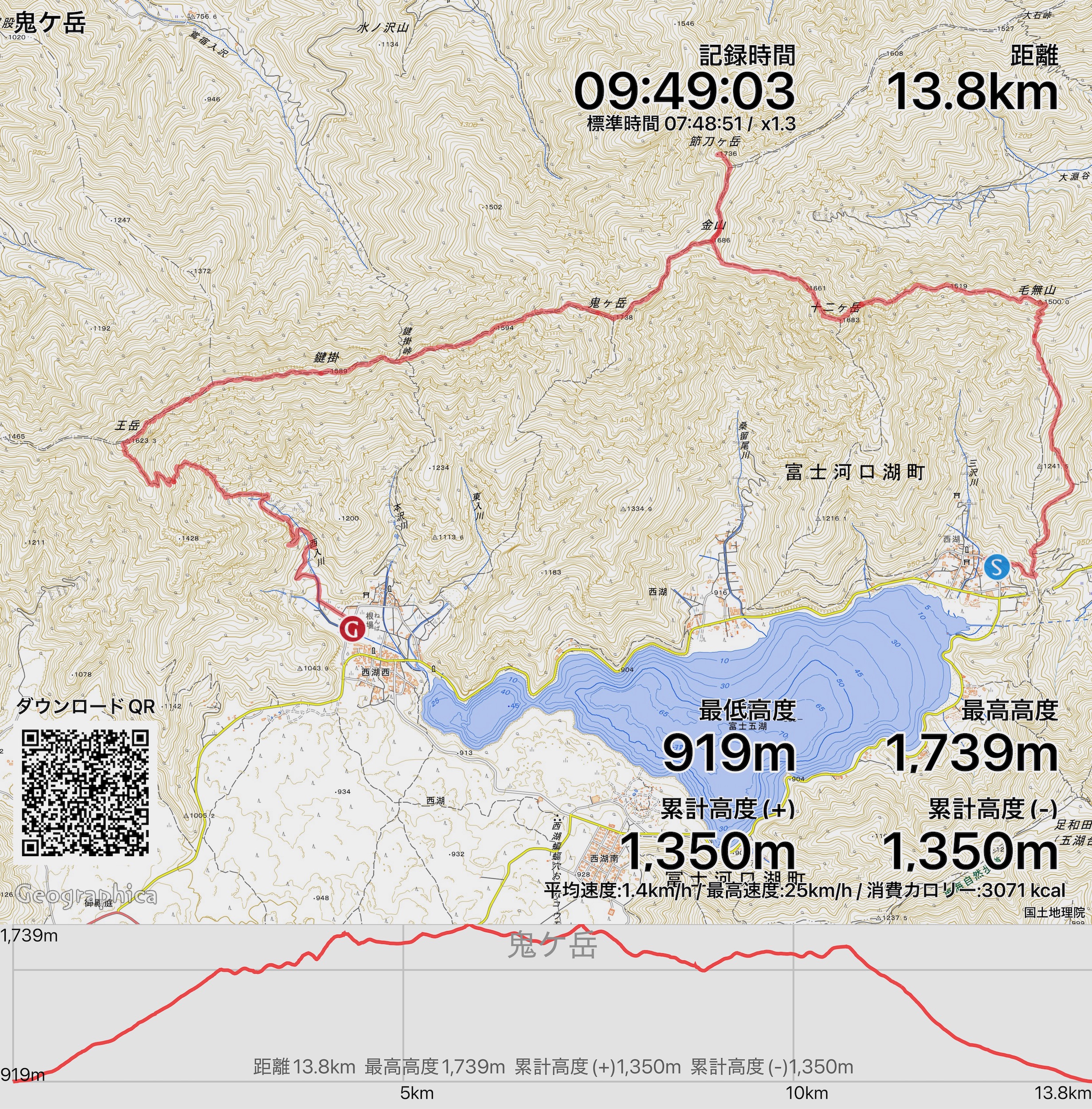
===============================================================�@
�@�@�@�@2025�N3��20�� �i�j�@���@�@�P��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�R�� 2013.2m�@
===============================================================
�O���̍~��ƍ����̉����\��Ɋ��҂��ĎR���ɂł�����
�撅�̒P�Ƃ̌�X�^�[�g�v���Ԃ�ɓo�R���߂�����ϐ�A�H���܂ł͓o��₷���ϐ��ԁB
�����܂łŐϐႪ����悤���Ƃ��̐�͂����Ƒ�����͂��Ȃ̂ŃA�C�[����
1600m��Ō�납��P�Ƃ�����ǂ������Ă������ƂĂ��Ȃ��͋����X�e�b�v�ŃA�C�[�������̑f�����o��ł����ɏ����Ă��܂���
1800m�����肩��ϐ�ʂ����������Ζʂ̓o��ɂ������������B
1900m��ł����قǒǂ������Ă������P�Ƃ������삯�~��Ă���^^;
�ƂĂ��Ȃ������A�g�������͂�͂�R�����̓o�R�҂Ƃ͕ʂ��Ȃ��Ǝv�����i�A���s�j�X�g�����l�̔n�͂ł��ˁj
��Ő�ɓo�����P�Ǝ҂��É��ł͗L���ȃg��������1�l���Ƌ����Ă��ꂽ�B
�R���͎c�O�Ȃ���x�m�R���ʂ̓O���[�̃K�X�ɕ�܂�܂�����莋�E�͖������̂�����A���v�X�A��͐�ɂ��ꂢ�ɔ����P���Ă���
�������₩�ƌ����Ă����e���Ă���Ɨ₽�������݂Ă����̂ʼn��R�J�n
���R���n�߂Ă����ɂ܂��P�Ƃ��o���Ă����B�ނ���͂�m�[�A�C�[���̑����͋����X�e�b�v�ŏ����Ă������������B
�͋����X�e�b�v�őf�����o�����X�œo�邽�ߍ����̂悤�Ȑ��Ԃł̓A�C�[���ȂǕK�v�Ƃ��Ȃ��悤��
���̎��ł͂Ȃ����Lj�����������m�ۂ��Ă��玟�̑����o���Ƃ����悤�ȃm���C����ł͒ǂ����Ȃ�^^;
�o���������������O�Ɏ��̑����o���X�s�[�h���Ȃ��ƈ��肵���o�����X���ێ����邱�Ƃ͂ł��Ȃ�
�i�N������邯�ǕG���ɂ��Ƃ���������������(;_;)�j
�H���ŃA�C�[�����O���X�}�z�̏[�d���Z�b�g�A�R���Őϐ�̒��ɃX�}�z�𗎂Ƃ����̂�
���C�g�j���O���������o�ŏ[�d�ł��Ȃ��ƃ��b�Z�[�W���ł����A�G�C���b�Ƌً}���Ԃ̃{�^����������
�[�d���s�����ŊO�����i���̂Ƃ���X�}�z�ɖ��͋N���Ă��Ȃ�^_^;;)
�H���ł������Ƃ��Ă���ԂɎR���߂��ŏo�������g���������삯����Ă�����
������������������K�ɍ~��ė\��ʂ�̎��Ԃʼn��R
����̂��Ƃ����Ǔo�R���߂��̃~�c�}�^���B���Ă���
���R��̕��C��16�����ߐ�Ȃ̂ŋ}���Ŏx�x�����ėѓ��𑖂����瓹�H�C�����������{���\�ʂ�Ɍł߂�܂ł��炭�҂��ƂɁB
���������Ă��炢���X�}���Ŏ��Ԃ܂łɕ��C�ɓ����B
�����ł݂��獡�������17�����ߐ�ɕύX�ɂȂ��Ă���^^;
���C�Ŏ��Ԓ��������ėz�̗����������ɏ���T�̂悤�ȏ�Ԃ��Č��ł��邩���m�F���Ȃ���A���
����͕��i�ƕς��Ȃ���ԂȂ̂ł��̐�ǂ����邩�Y�ނƂ��낾
�ʐ^�P�@�������x�����i�E�j�@���͏�͓��x�@�E�͐ԐΊx�Ə��ԐΊx

�ʐ^�Q�@���̕W���̌��ɕx�m�R������̂���(;_;)

8:28
�����e��o�R��
9:08 ���@9:14
9:38 ����
10:00 �H���@10:10
11:56 �R������
12:11 �R���@12:46
12:54 �R������
13:00 �����~��n�_
13:54 �H���@14:14
14:27 ����
14:41 ���
15:07 �Ԃɖ߂�
3/25�ɃX�v�����O�E�G�t�F����������ŖL���Ί�����̃J�^�N����
�V����g�̃J�^�N���Ɩ��_�R�̃V���E�W���E�o�J�}���Q�b�g
�V��̃J�^�N���͂����I���ɋ߂�����


===============================================================�@
�@�@�@2025�N3��26�� �i���j�@���@�@�P��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����x�@1144.8m�@
===============================================================
26���������Ŏ��E�悭�Ȃ��̂ő����̉Ԃ�T���ɁA����ƕW����1000m�ʏ��Ńg���[�j���O�ɂȂ�R��
�����Ȃ�Ă邩�Ǝv�����畟�����̎����̂��������ԏ�͖��Ԃɂ����������A
�z�������肾���Ă���̂ق����J�Ԃ��Ă���Ǝv���X�^�[�g��x�点�����Ƃ��e����������
�����ڂ܂ł͏������𗬂��Ȃ���̒P���ȓo��A��������c�Ⴊ����n���ēD�^��Ԃ��n�܂�
1000m������Ő��̕������������`�F�b�N���ĎR���Ɍ�������
�R���͐l�������̂ő��u�c�R�����̓W�]��ɍs���A�ׂ̎R�e�͂������Ɍ�������x
���͗�������������Ă���Ζ��Ȃ��̂ŏ��������ɂ��ꂽ
�R�����o�R���Ă��̂܂܉��R��
�~�肾���Ă����ɕ����������������Ɍ������Ԃ������Ċy����
�����ڂ���͍ēx���𗬂��Ȃ���فX�ƍ~��Ԃɖ߂���
����ނ�A�H�ɂ���
�������̍����͘p�݂𗘗p���邹���������͐É����ʂɔ�ׂĒZ���������͍����̂����_(;_;)
�ʐ^�@�t�N�W���\�E���낢��@�ꏊ�͑S���قȂ�
 �@�@
�@�@
8:47
��L�˔������ԏ�o
10:06 ������
10:49 �����R��
11:05 �R��
11:15 �R���W�]��@�@11:36
11:46 �R���@11:53
12:05 �����R��
13:05 ������
13:54 �Ԃɖ߂�
2025�N�g�b�v��
2024�N�g�b�v
��
2023�N�ꗗ�֖߂�
2022�N���A��o�R��
2021
�N���A��o�R��
2020�N���A��o�R�g�b�v��
2019�N���A��o�R from�L����
2018�N���A��o�R�g�b�v��
2017�N�P�Ɠo�R�g�b�v��
2016�N���A��o�R��
2012�N�g�b�v��
2011�N���A��o�Rfrom �L���s�g�b�v��
2010�N���A��o�Rfrom �L���s�g�b�v��
2009�N���A��o�Rfrom �L���s�g�b�v��
2008�N���A��o�Rfrom �L���s��
�z�[ ���֖߂�
�� ��




 �@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@







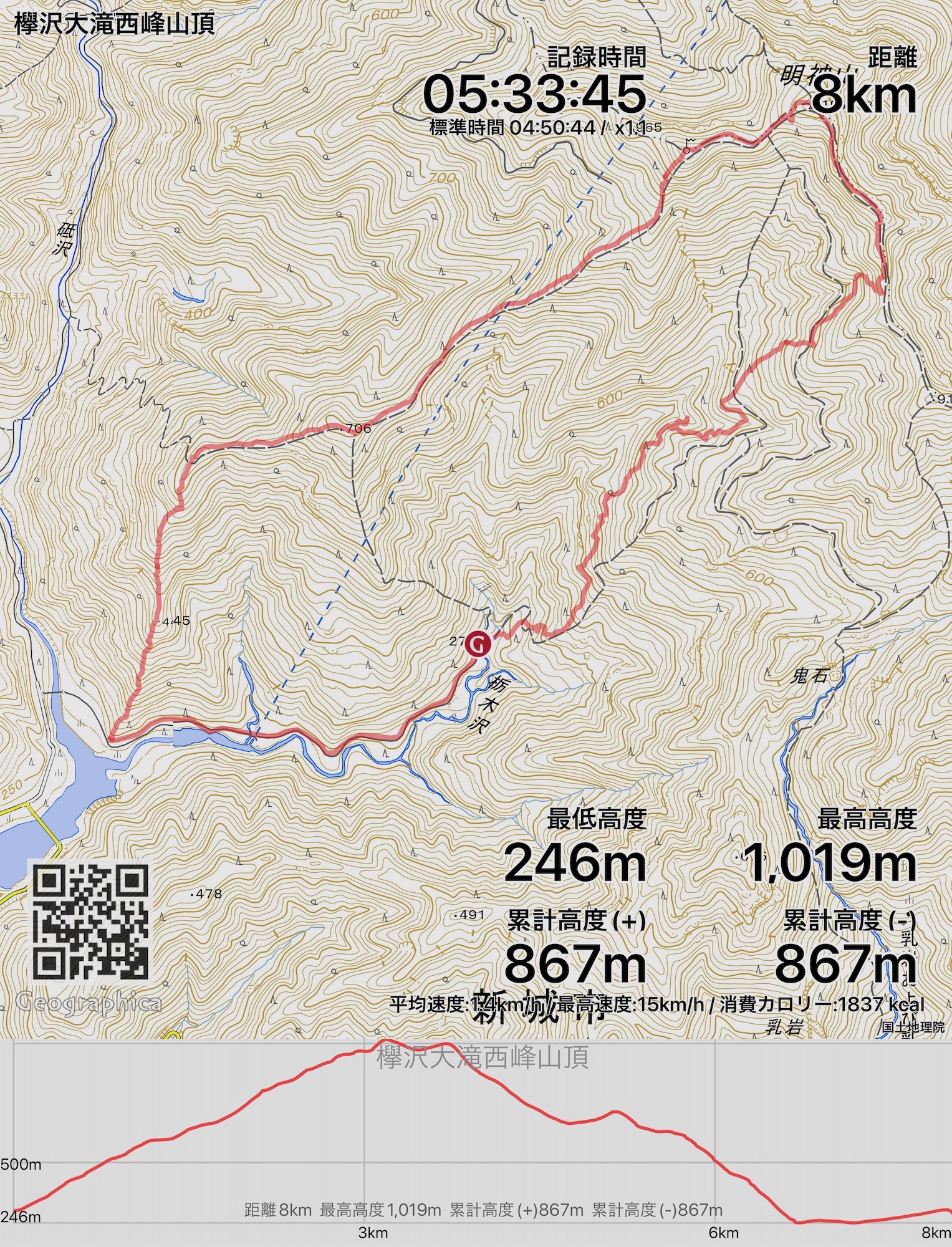


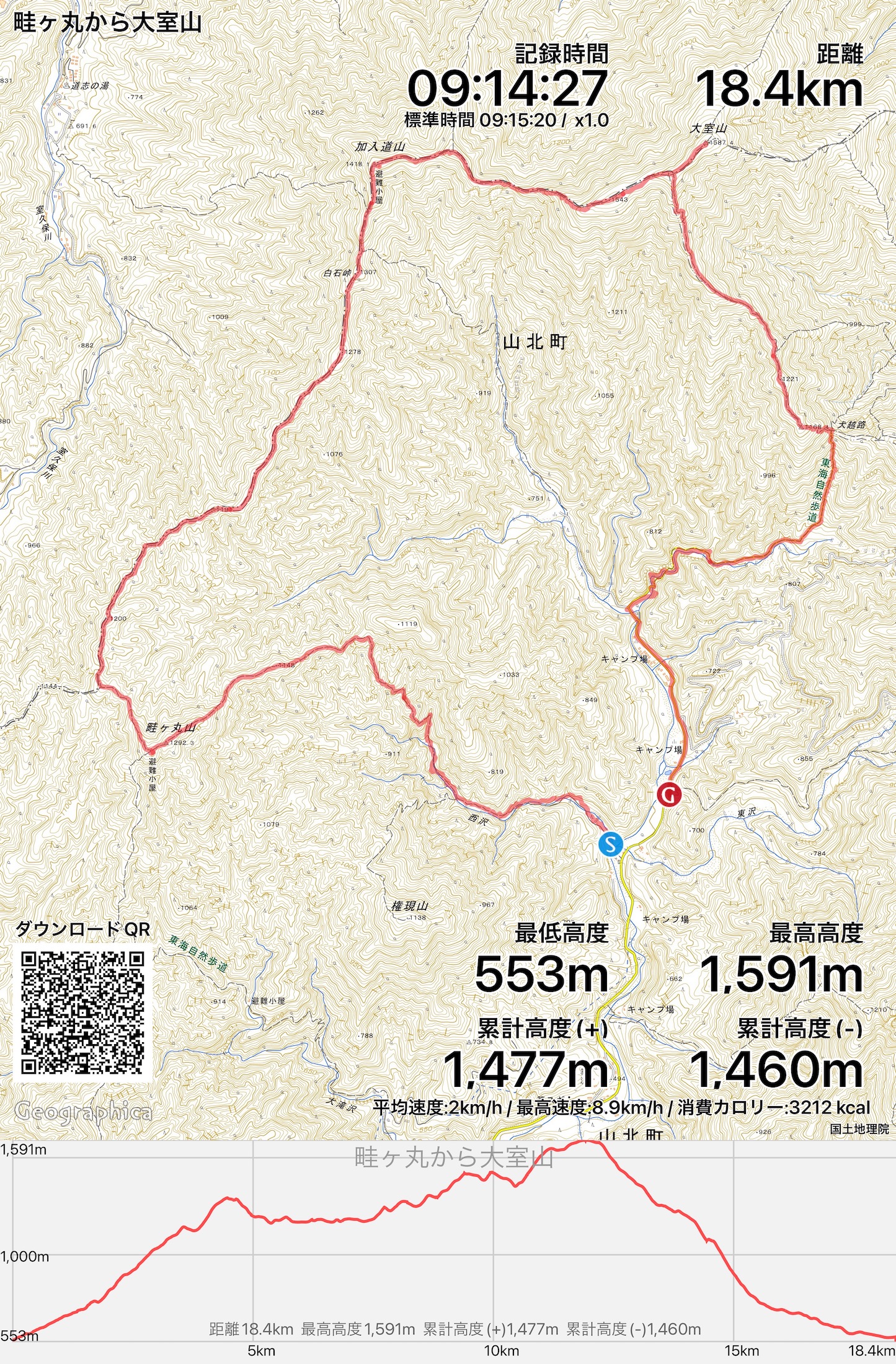











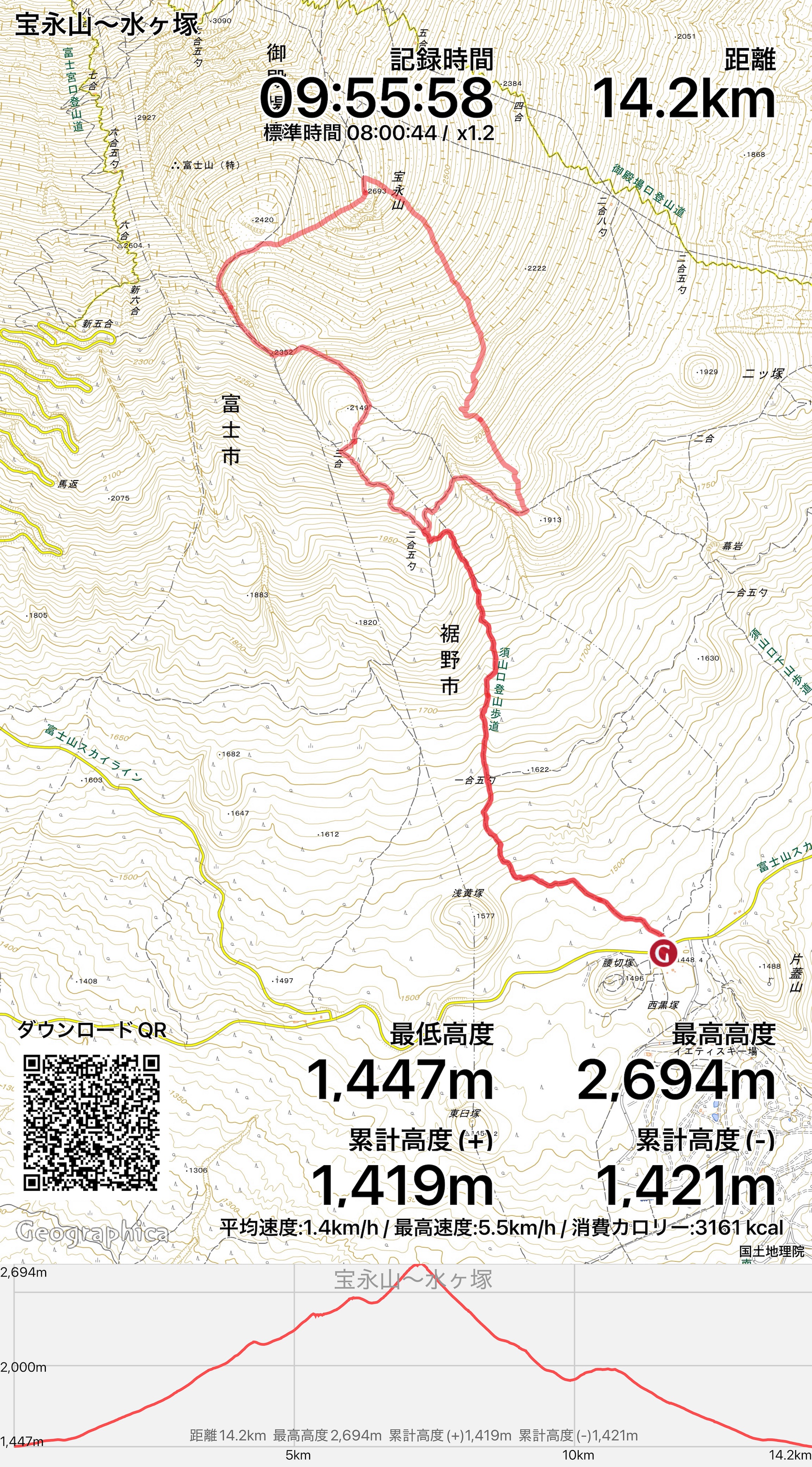


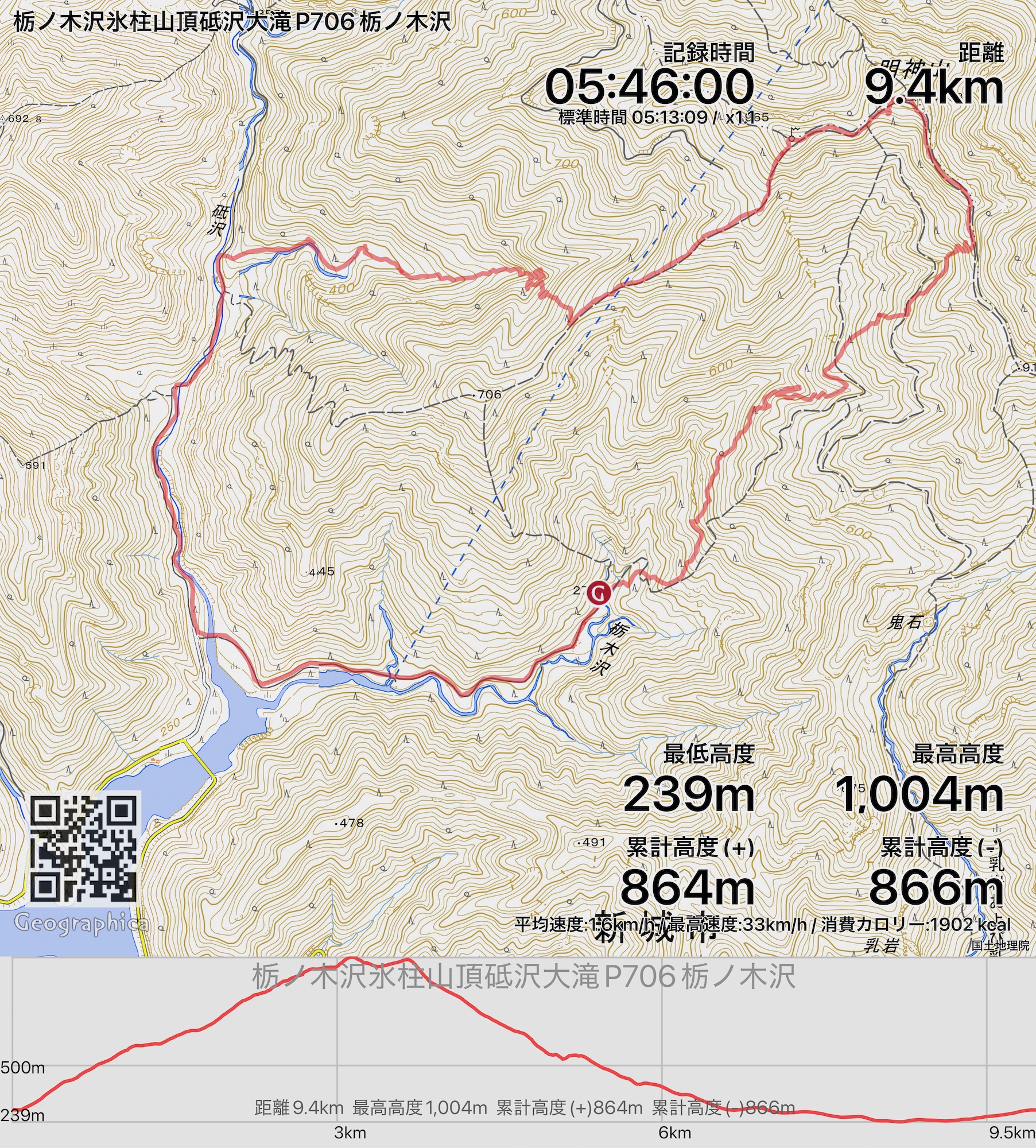









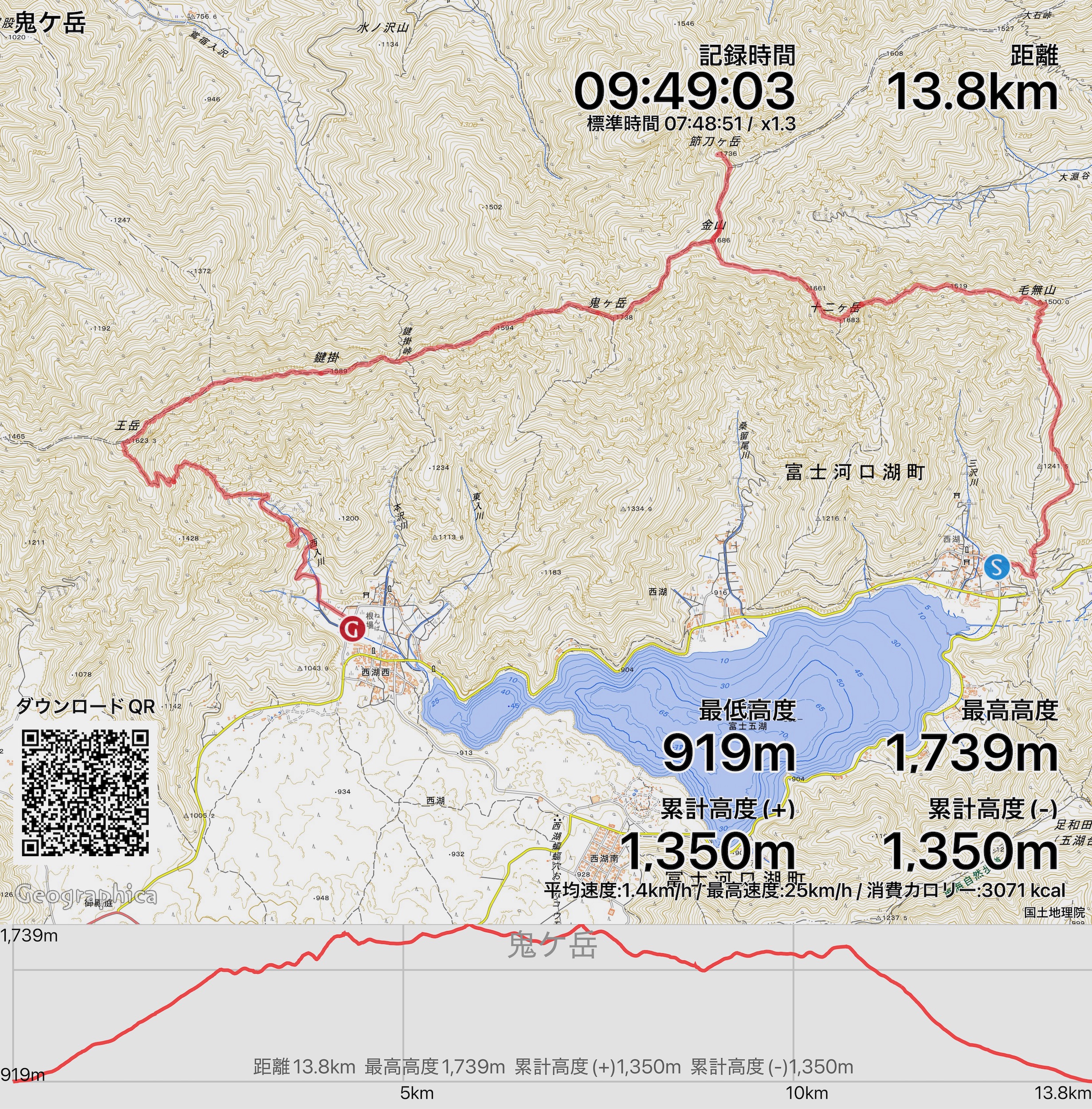




 �@�@
�@�@